🍀数字に心
🍀税に愛
🍀人生には笑いと熱き想いを
🍀税に愛
🍀人生には笑いと熱き想いを
- ホーム
- ブログ
- お布施ブログ100チャレンジ2025
- 【48】ここが変だよ日本の税制 ~日本をせんたく致し申し候~
【48】ここが変だよ日本の税制 ~日本をせんたく致し申し候~
2025/02/17
【1】今、米の値段が大幅に上がっている
国には備蓄米がたくさんあるにも関わらず、である。
原因は米が足りなくなったからではない。
米の流通経路が多角化したため、
国側はもはや市場に出回っている米の流通量を
正しく把握できなくなってしまっており、
米を備蓄すべきか放出すべきかのタイミングを
正常に判断できない事態に陥っている。
このことは先日の農水大臣の謝罪にも明らかだ。
問題はそれだけではない。
食文化の多様化に伴い、米が余り過ぎるので、
国は、国民の血税を投入してまで減反政策を推し進めてきた。
にも関わらず、今、われわれは、
わざわざ高い値段の米を買わねばならない。
わざわざ高い値段の米を買わねばならない。
税を注入して、高いコメを買う事態・・・
なんとも皮肉な話である。
【2】おかしいのは米だけではない
道路インフラ整備のために「あくまでも一時的に」という約束で
導入されたガソリン税は、もはや完全に恒久化されてしまっている。
しかも、ガソリン税という税にさらに消費税が賦課されるという、
消費税法の立法趣旨から見てもおかしな事態となっている。
消費税率にしても、
諸外国に比べて日本は低いので、これを上げようとする動きがあるが、
消費税以外の税目や社会保険を合算して見れば、
日本が如何に他国よりも負担割合の高い国であるかは明らかだ。
輸出免税により消費税還付を受ける大企業により構成される経団連が
消費税率UPに異を唱えないのも、
都合の良い「我田引水」な持論としか思えない。
【3】ふるさと納税にしてもそうだ
ふるさと納税をすればするほど、
自分が住んでいる地元自治体の税収が減ってしまうというのは
住民税の根幹をなす「受益者負担の原則」を根底から覆すものだ。
しかも、高所得者ほど多額の減税効果を得られるので、
税の大前提である「課税の公平性」の観点からも問題だ。
確定申告不要として後発導入された「ワンストップ方式」に至っては、
さらに地方自治体の悩みのタネとなっている。
なぜなら、確定申告でふるさと納税を控除する場合であれば、
まずは国税(所得税)から控除し、
残りを住民税から控除するというスキームとなっているが、
ワンストップ方式はいきなり全額が住民税から控除されるからだ。
わが国の地方自治運営は、東京都以外は独立採算がとれていない。
よって、結局は、国からの地方税交付金で各市町村は財布を補っているので、
自治体にカネが足りなければ国庫から補充して貰えば良いだけの話、
という趣きがあることも分かる。
しかし、ふるさと納税が地元の税収を悪化させるがために、
それが「国庫からの注入補てん」という事態となり、
挙句には、国庫としても財政状態が厳しくなってしまい、
結果、昨今の法律改正(あるいは改正案)のように、
各種の税や社会保険負担が増えれば、
各種の税や社会保険負担が増えれば、
そもそも何のためのふるさと納税なのか、
全くその意味を見出せない。
【4】日本人の寄付精神
日本人は欧米人に比べて「寄付意識」が低い国民だと言われている。
しかし、その一面だけを持って「公平な相対比較」はできない。
何故なら、日本人ほど真面目に納税する国民も世界的には珍しいからだ。
お上(オカミ)には逆らわないで従う・・・封建社会や江戸時代を経て、
良くも悪くも、いまだにその意識が抜けていないのかも知れないが、
そもそもこれだけ真面目にきちんと納税し、文句も言わず、
暴動も起こさない国民性というのは世界的に見ても珍しい。
きちんと納税する国民性があるからこそ、
徴収された税が各方面へと分配されるので、
寄付という文化が根ざさなかったのも容易に推測できる。
よって、寄付の一面だけを取り上げて、
「日本人は寄付精神が低い」と指摘するのは
あまりにも稚拙すぎると言えよう。
但し、安倍内閣の頃に立法された地方創生という考えのもと、
地方自治体にも競争原理を取り入れて、
地域を活性化させようとするその意図は一定割合理解できる。
しかし、過度の返礼品競争を引き起こしてしまい、
最終的にはやり過ぎた自治体はお上からやり玉にあげられ、
叱責を受ける事態となってしまった。
いわば「商売っ気」のある自治体ほど、
お上から頭を押さえられたということだ。
こうなると本当に、国は地方に何をさせたいのか、
どうなって欲しいのか、甚だ分からなくなってくる。
【5】日本を<せんたく>いたし申し候
税法の根本は民法であり、ヒトだ。
法の前にヒトありき、であって、
ヒトの前に法ありき、であってはならない。
幕末、坂本龍馬はこう述べた。
日本を今一度、せんたくいたし申し候
まさにそのような心境となってしまうのは、
私だけではないのではないだろうか?
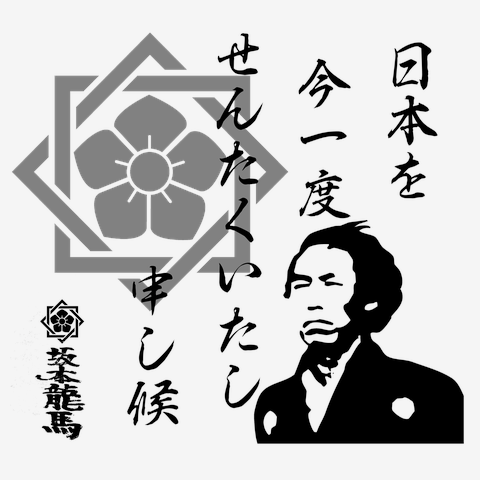
関連エントリー
-
 連続税務小説 ヤマゲン 第28話「“税務調査を呼ばない会社”の作り方」
ヤマゲンは、 売上表でも 決算書でもなく、 試算表を机に広げた。「田中さん」 ネクタイのイチゴ柄を、 指で軽
連続税務小説 ヤマゲン 第28話「“税務調査を呼ばない会社”の作り方」
ヤマゲンは、 売上表でも 決算書でもなく、 試算表を机に広げた。「田中さん」 ネクタイのイチゴ柄を、 指で軽
-
 連続税務小説 ヤマゲン 第29話「“税務調査が来ても慌てない会社”の共通点」
ヤマゲンは、 珍しく何も説明せず、 コーヒーを一口飲んだ。 イチゴポッキーも、 まだ開けない。「田中さん」 静
連続税務小説 ヤマゲン 第29話「“税務調査が来ても慌てない会社”の共通点」
ヤマゲンは、 珍しく何も説明せず、 コーヒーを一口飲んだ。 イチゴポッキーも、 まだ開けない。「田中さん」 静
-
 連続税務小説 ヤマゲン 第30話「税務調査が終わったあとに“必ずやるべきこと”」
税務調査が終わった翌日。 田中 恒一は、 何もない事務所で、 一人、机に向かっていた。 調査官はいない。 書類
連続税務小説 ヤマゲン 第30話「税務調査が終わったあとに“必ずやるべきこと”」
税務調査が終わった翌日。 田中 恒一は、 何もない事務所で、 一人、机に向かっていた。 調査官はいない。 書類
-
 連続税務小説 ヤマゲン 第31話 「青色申告を、甘く見た日」
月末の夕方。 田中 恒一は、工場の電気を一つずつ落としていた。 機械の音が止まり、 静けさが戻る。 その静け
連続税務小説 ヤマゲン 第31話 「青色申告を、甘く見た日」
月末の夕方。 田中 恒一は、工場の電気を一つずつ落としていた。 機械の音が止まり、 静けさが戻る。 その静け
-
 連続税務小説 ヤマゲン 第32話 「法人にした方がトクなんですか?」
昼過ぎ。 町工場に差し込む日差しが、 以前より少し強く感じられた。 機械の音は止まらない。 注文も、 問い合
連続税務小説 ヤマゲン 第32話 「法人にした方がトクなんですか?」
昼過ぎ。 町工場に差し込む日差しが、 以前より少し強く感じられた。 機械の音は止まらない。 注文も、 問い合
竹岡税務会計事務所
経営が見えない!を数字でクリアに。
まずは、お気軽に無料相談を。
電話番号:090-7499-8552
営業時間:10:00~19:00
定休日 : 土日祝
所在地 : 大阪府富田林市須賀1-19-17 事務所概要はこちら