🍀税に愛
🍀人生には笑いと熱き想いを
- ホーム
- ブログ
ブログ
【78】相続時精算課税制度を使った贈与の注意点
2025/03/19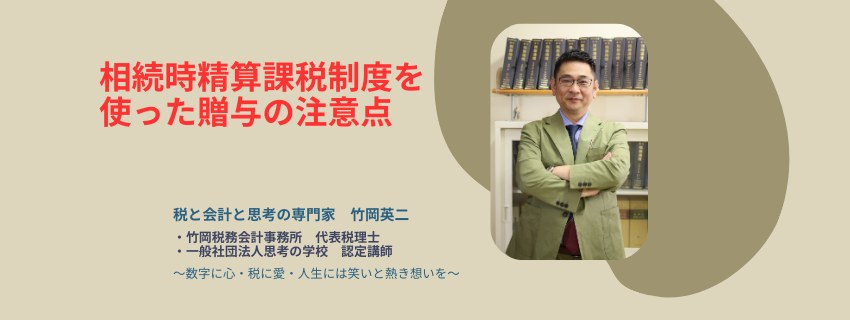
今日は
「相続時精算課税制度を使った贈与の注意点」
についてお話します。
「いやいや、注意点の前に、そもそも、そんな制度、知らんがな!」
さてさて、
暦年贈与とは違って、
年間110万円までであれば、
相続開始前7年間の贈与財産が
相続財産に加算されることがないんです。
相続開始年分の贈与に関しても、
基礎控除額110万円が適用されます。
ちなみに、令和5年において、
相続時精算課税による贈与を受けた人は約4.9万人いるようです。
令和6年の実績数はまだ分かりませんが、
今後はさらに増えると思われます。
ここで、みなさんに覚えておいて欲しいことがあります。
それは・・・
相続時精算課税による贈与は
- 毎年110万円までの贈与額:贈与者の相続財産に加算されない
- これを超える金額:贈与者の相続財産に加算される
・・・という「当たり前のこと」です。
例を挙げてみますよ。
🔴 被相続人:父親
→ 相続時精算課税による贈与を使った贈与者
🔴 相続人:子供3人(長男、次男、三男)
→ 長男は相続時精算課税による贈与を使った受贈者
→ 贈与額は3,000万円(令和6年に1度に行なった)
🔴 被相続人の相続財産として、
3,000万円-110万円=2,890万円が加算される。
この場合、
長男さんだけに3,000万円を贈与したって事実が
相続税申告の際に、他の相続人に分かってしまうのです。
なぜなら、相続税申告書には、その旨がバーンと書かれているので。そうなると、次男さんや三男さんはどう思うでしょうか?
もちろん、これが問題にならないケースもあるでしょう。
正直なところ、
税金のことよりもこちらの方が問題💦
相続時精算課税による贈与は
「税金のこと」を考えて実行されることが多いんです。
しかし、これを優先させたが故に「相続人の人間関係が壊れた」
ということにもなりかねないんですよね。
当たり前ですが、このことは祖父母から孫への贈与でも
同じことが起き得ます。
相続人(子供)が複数いる場合でも、
「特定の孫にだけ相続時精算課税による贈与をする」
ということがあり得るからです。
なので、ぼくはお客様に・・・
- 贈与をするなら、相続人間で平等に行うのが原則
- 子どもの産まれた年が違い、贈与開始年が違うならば、何かしらの形式で帳尻を合わせる必要がある
(→ 例:贈与税を支払った後の「手取り額の総額」で調整)
・・・ということもお伝えしています。
法人税であれ、所得税であれ、相続税であれ、
税金を減らすことは簡単です。
しかし、税金を減らす行為が
本末転倒になってしまっては意味がないのです。
さらに大切なのは「節税」ではなく、
「税引き後のお金を増やすこと」なのです。
しかし、多くの方が
「税金を減らすことを意思決定の第1ステップにしてしまっている」
という現実があります。
こんなことじゃ、
相続であれ、事業承継であれ、会社の経営であれ、
「物ごとの本質」を見誤っちゃいますよね。
NGな意思決定:「この方法を採用すれば、税金が減る」
OKな意思決定:「この方法を採用した方がいいし、結果として税金も減る」
ぼくのクライアントさんからも、よく
「こういう風にすれば税金が減るが、どう思いますか?」
というご質問が出ることがあります。
しかし、その多くは「物ごとの本質」から逸脱した方法なのです。
繰り返しますよ。
大切なのは
「物ごとの本質から逸脱しないこと」
これらを見誤らないようにしてくださいね🌈
【77】確定申告、無事終了 ~そして、思うこと~
2025/03/18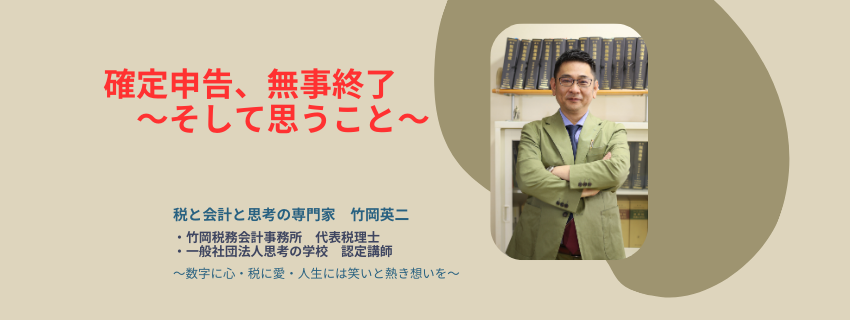
【76】家計簿も会社の会計も同じ?
2025/03/17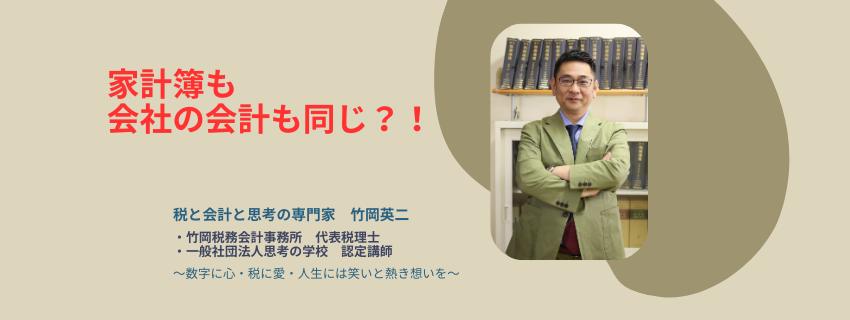
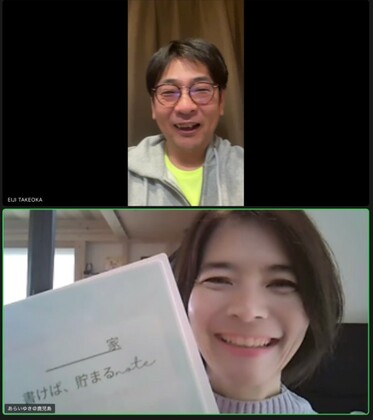
【75】未来を共に描けるか?
2025/03/16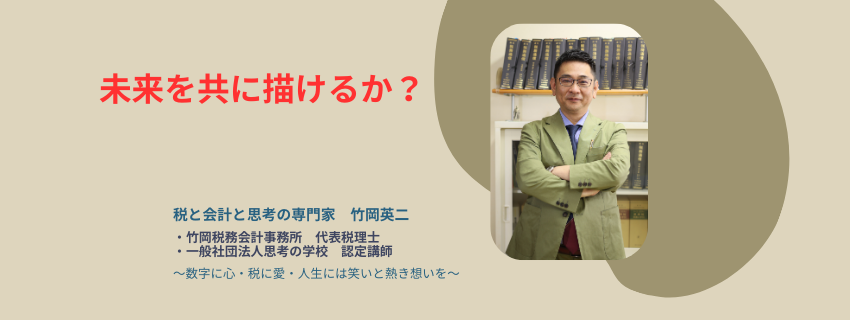
【74】なんのために100km歩くのか?
2025/03/15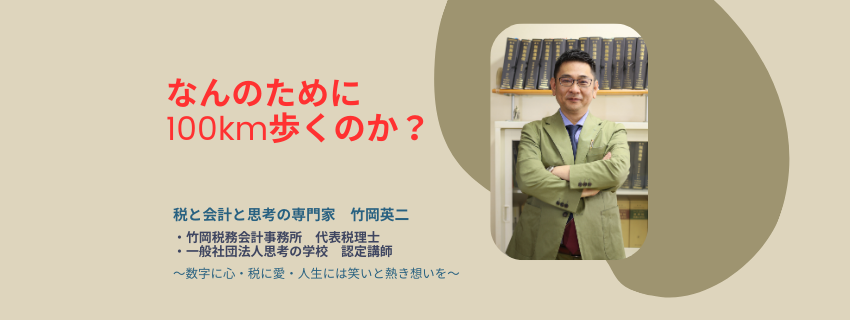
竹岡税務会計事務所
経営が見えない!を数字でクリアに。
まずは、お気軽に無料相談を。
電話番号:090-7499-8552
営業時間:10:00~19:00
定休日 : 土日祝
所在地 : 大阪府富田林市須賀1-19-17 事務所概要はこちら