🍀税に愛
🍀人生には笑いと熱き想いを
- ホーム
- ブログ
ブログ
【68】カンニングしたらイイんです
2025/03/09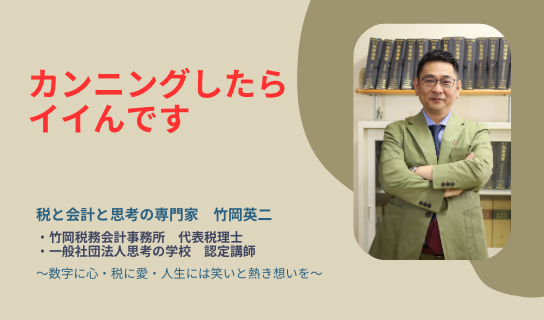
【67】相続放棄の手続きの実際とその流れ
2025/03/08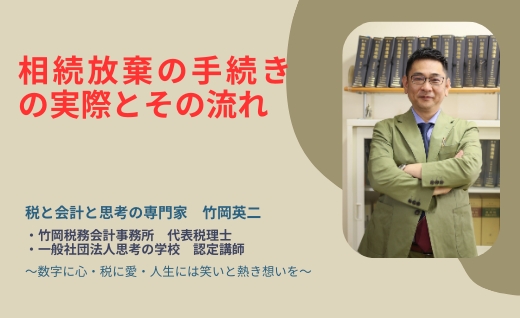
相続における3つの選択
相続が発生すると相続人となる者は
- 単純承認(プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する)
- 限定承認(プラスの財産の範囲内でマイナス財産を引き継ぐ)
- 相続放棄(遺産の相続を放棄しプラスの財産もマイナスの財産も一切相続しない)
・・・のいずれかを選ぶことになります。
相続放棄を選択するのは、一般的に借金が多い場合と考えられますが、
借金がなくとも相続にかかわりたくない、
財産分与ゼロでハンコを押すのはシャクだなど、
他の理由であっても自分の意思で選べます。
相続放棄の手順
(1)家庭裁判所へ相続放棄を申述する
相続放棄の申述は、民法により、
自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所にしなければならない、
と定められています。
申述書に申述内容を記入し、
被相続人の住民票除票又は戸籍附票や申述人(放棄する人)の戸籍謄本など(=申述人の被相続人との関係性により必要書類は変わってくる)を添付して
家庭裁判所に書類を送ります。
(2)家庭裁判所から「照会書」が届く
申述後、家庭裁判所から「照会書」が届き、
- 誰かに強要されたり、
- 他人が勝手に手続きしたり、
- 相続放棄の意味がわからず手続きしていないかなど、
その申述が本人の真意によるものかの確認がなされます。
(3)「相続放棄申述受理通知書」で完了
家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」(相続放棄が無事に認められた旨の通知)
が届いて手続き完了となります。
なお、他の相続人が相続手続きをする際に
「相続放棄申述受理証明書」の原本が必要となります。
通常は、受理通知書が届いた後に受理証明書の交付申請を行いますが、
事前に受理証明書の交付申請を行えば
受理通知書に同封されて受理証明書も届きます。
相続放棄のデメリット
相続放棄が完了すると後から撤回できないため、【66】相続した不動産の登記を放っておくと罰金がかかります
2025/03/07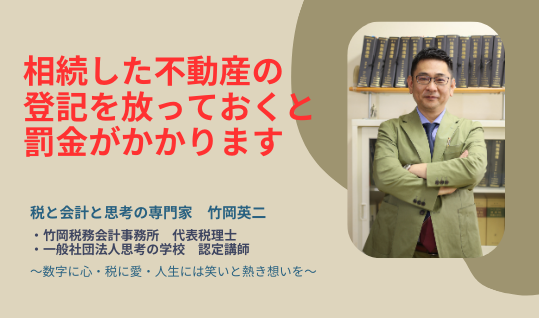
相続登記の申請の義務化(2024.4.1施行)
相続等により不動産を取得した相続人は、
その所有権を取得したことを知った日から3年以内に
相続登記の申請を行う必要があります。
また、遺産分割協議が行われた場合は、
遺産分割が成立した日から3年以内に、
その内容を踏まえた登記を申請する必要があります。
これらの登記懈怠には10万円以下の過料が課せられます。
なお、遺産未分割で、相続登記不可の場合は、
自分が相続人であることを法務局の登記官に申し出れば、
相続登記の申請義務履行とみなされます。
10年経過遺産の相続分(2023.4.1施行)
被相続人の死亡から10年を経過した後の遺産分割は、
原則として法定相続分によって画一的に行うこととされます。
住所変更登記義務化(2026.4.1施行)
登記簿上の不動産の所有者は、
所有者の氏名や住所を変更した日から2年以内に
住所等の変更登記の申請を行う必要があります。
登記懈怠には5万円以下の過料が課せられます。
なお、公的機関間情報による登記官職権登記も始まるので、
この職権登記があると、
住所等の変更登記の申請義務は履行済みとなります。
ただし、自然人の場合には、本人の了解が前提です。
DV被害者保護登記(2024.4.1施行)
DV被害者等を保護するため
登記事項証明書等に現住所に代わる事項を記載する特例があります。
所有不動産記録証明制度(2026.2.2施行)
不動産登記名義人の住所と氏名を全国的に一括して調査し、
所有不動産記録証明書というリストで証明する制度が始まります。
被相続人名義の不動産だけでなく、
存命の名義人や法人名義の不動産も調査できます。
請求人は本人、相続人、法定代理人等に限定です。
相続土地国庫帰属制度(2023.4.27施行)
国庫帰属申請をするには、
1筆の土地当たり1.4万円の審査手数料が必要であり、
審査を経て承認されると、
10年分の土地管理費相当額の負担金が必要です。
負担金額は原則20万円です。
共有制度の見直し(2023.4.1施行)
●共有物に軽微な変更では、全員の同意は不要、過半数持分で決定、【65】ECサイトの電子取引データ保存
2025/03/06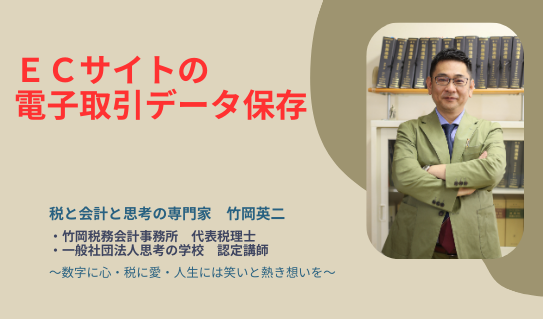
令和6年1月より事業者に電子取引データの保存が義務付けられましたが、緩和措置もあります。
◆ECサイトで物品を購入した場合
ECサイトでの取引記録は電子取引データとして保存が求められます。
ECサイトの取引記録はダウンロードまたはPDFにて保存しますが、
ECサイトで領収書等の取引データを随時確認できる場合は、
必ずしもダウンロードして保存する必要はありません。
なお、「検索機能の確保」については、
基準期間(取引の行われた年の前々年)の売上高が5000万円以下の事業者、
または、
電子取引の記録を書面で出力し、取引年月日その他の日付、取引金額、取引先ごとに整理して提示・提出できるようにしている事業者が、
税務職員の求めに応じて当該取引データをダウンロードできるようにしている場合は、
検索要件を満たしているものとして取り扱われます。
◆クレジットカードで購入した場合
ECサイトで購入した物品の支払をクレジットカードで行う場合、
カード会社の利用明細も電子取引に該当し、
電子取引データとしての保存が必要になります。
この場合も利用明細をカード会社のサイトで随時確認できればダウンロードは必要ありません。
◆インターネットバンクの利用記録で保存
ECサイトで購入した物品の支払代金をインターネットバンキングを利用して振込、またはクレジットカードで引落した場合も
EDI取引として電子取引データとしての保存が必要になります。
この場合もオンライン上の通帳や入出金明細等で利用記録を確認できればダウンロードは必要ありません。
◆WEBサイトの保存期間に注意!
一方、税法上の領収書等の保存期間は、青色申告で原則7年、白色申告で5年ですが、
これらの期間、WEBサイトで取引データが保存されないことがあります。
この場合、WEB上のデータが確認できなくなる前に、ダウンロードまたはPDFで保存する必要がありますが、
WEBサイトで確認できるようになった段階での随時保存も有用といえます。
◆電子インボイスの保存
ECサイトで購入した物品の領収書等は、適格請求書等(電子インボイス)となりますが、【64】申告書に収受印を押してくれない
2025/03/05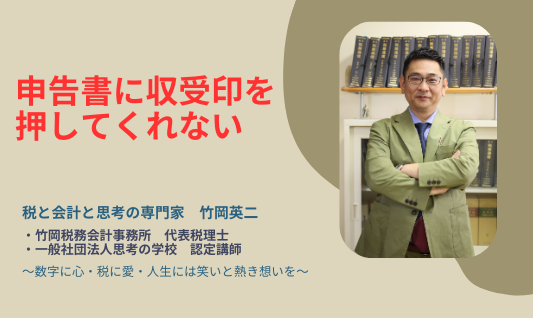
◆令和7年1月以後は
国税庁は今年1月4日、
『令和7年1月以後は『申告書等の控えへの収受日付印(税務署名や年月日等)の押捺を廃止する』と公表しました。
これは申告書等の持参又は郵送に対する措置です。
e-Taxによる申告では『受信通知』がメッセージボックスに格納されます。
税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(DX)の取組の推進が目的です。
また、令和7年1月から、申告書等の提出(送付)の際は、申告書等の正本(提出用)のみを提出(送付)するように、と公示しています。
◆申告書等提出事実を証明する方法
それでは、申告書等を紙で提出する場合、今後はどのように申告等したことを証明すればよいのでしょうか。
①国税庁が公開したQ&Aによりますと、
令和7年1月以後の当分の間の対応として・・・
窓口で交付するリーフレットに申告書等を収受した日付や税務署名を記載した上で希望者に配付する、
この配布文書は提出事実の証明機能を持つ・・・と回答しています。
②所轄税務署に「申告書等閲覧申請書」を提出することで、
申告済みの申告書等を閲覧することができます。
そこには収受印が押されています。
閲覧に手数料はかかりませんが、あくまで閲覧サービスのため、
コピーの提供は受けられません。
ただし、申請書の「写真撮影の希望」欄にチェックをつけることで
写真撮影が可能となります。
③納税証明書の交付請求を行い、
納税額と滞納の有無の表示を介して、提出済み申告書の内容を間接的に証明します。
④個人だけのケースとしては、
申告書等情報取得サービス(オンライン請求のみ)、
保有個人情報の開示請求(写しの交付請求は1か月程度)
などがあります。
◆銀行等は対応を変えないと
これまでは・・・竹岡税務会計事務所
経営が見えない!を数字でクリアに。
まずは、お気軽に無料相談を。
電話番号:090-7499-8552
営業時間:10:00~19:00
定休日 : 土日祝
所在地 : 大阪府富田林市須賀1-19-17 事務所概要はこちら