🍀数字に心
🍀税に愛
🍀人生には笑いと熱き想いを
🍀税に愛
🍀人生には笑いと熱き想いを
- ホーム
- ブログ
- お布施ブログ100チャレンジ2025
- 【86】おすすめの1冊「歴史にふれる会計学」
【86】おすすめの1冊「歴史にふれる会計学」
2025/03/27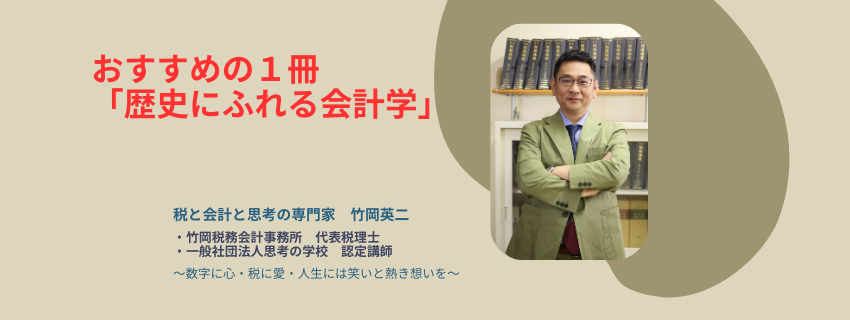
法人・個人事業を問わず、
経営者は会計とは無関係ではいられません。
日々の会計処理・月次試算表・決算書など、
色々な場面で会計は登場し、
そして、経営者にその理解能力と読解力を求めてきます。
書店、あるいは、インターネットショッピング上には
- これなら分かる***
- 経営者のための***
といった具合で、
経営者向けの会計や決算書に関する書籍が山ほどあります。
どの書籍も
- 簡単
- 分かりやすい
- これだけは知っておけば大丈夫
というキャッチーなタイトルで
経営者(読者)の関心を集めようとしていますが、
しかし、
この手の本が山ほどあるということは、
裏返して言えば、
それだけ会計や決算書は難しいと言うことの証拠
でもあるのです。
会計が難しいとされる理由は沢山あるでしょうが、
私が思うその理由の1つは、
実務的な面ばかりに目を向けすぎて、会計の面白さを知らない
という点です。
では、
「会計の面白さとはナンゾヤ???」となるのですが、
<ローマは一日にして成らず>と同じで、
何ごとにも歴史があり、
もちろん、会計にも歴史があります。
今、我々が取り組んでいる会計は、
もともと、ベニスの商人がやっていた経理法が起源です。
それをルカ・パチオリ(パチョーリ)という人が本にしたことで、
世界へ広がっていくこととなりました。
みなさんが「1年間」と当たり前のように思っている【会計期間】も
昔は1年ではなく【1航海】を会計期間としていました。
王様に出資してもらい、航海を通じて商売をし、
帰国後に王様に報告書を提出して利益を分配する、
・・・そういう航海時代も今の会計の背景になっています。
その後、産業革命により機械化が進み、
固定資産・減価償却という考えが生まれ、
徐々に現代の会計の形に近づいていくのです。
どうですか?
ちょっと興味がわきませんか?
もし「ちょっと面白いかも・・・」と思われる方には、
私のイチオシの1冊をご紹介します。
友岡 賛 著
歴史にふれる会計学
有斐閣アルマ
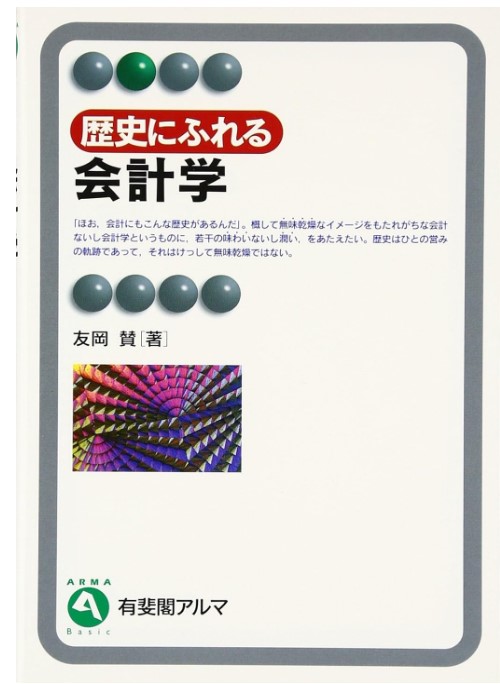
会計の歴史書は絶対数として非常に少なく、
しかも、その歴史的な成り立ちと発展について、
これほどまでにコンパクトにまとめあげた本は
結構珍しいのです。
顧問先の経理のオバチャンも「これ、面白いわぁ」と仰っていました(^^)
会計のことを「無味乾燥した存在」だと思っている方、
数字が苦手で仕方がないという方、
そんな方ほど、
この1冊を通じて、会計の歴史ロマンに触れてみて下さい。
この1冊を読み終えた後には、
日常的に向き合ってきた試算表や決算書の数字に対する印象が、
変わると思いますよ!
なお、あくまでも私の個人的なオススメの1冊ですから、
当然、好き嫌いはあるかと思いますが、
ぜひ、この本を手に取って、会計の歴史の面白さを知って頂ければ嬉しいです。
関連エントリー
-
 連続税務小説 ヤマゲン 第28話「“税務調査を呼ばない会社”の作り方」
ヤマゲンは、 売上表でも 決算書でもなく、 試算表を机に広げた。「田中さん」 ネクタイのイチゴ柄を、 指で軽
連続税務小説 ヤマゲン 第28話「“税務調査を呼ばない会社”の作り方」
ヤマゲンは、 売上表でも 決算書でもなく、 試算表を机に広げた。「田中さん」 ネクタイのイチゴ柄を、 指で軽
-
 連続税務小説 ヤマゲン 第29話「“税務調査が来ても慌てない会社”の共通点」
ヤマゲンは、 珍しく何も説明せず、 コーヒーを一口飲んだ。 イチゴポッキーも、 まだ開けない。「田中さん」 静
連続税務小説 ヤマゲン 第29話「“税務調査が来ても慌てない会社”の共通点」
ヤマゲンは、 珍しく何も説明せず、 コーヒーを一口飲んだ。 イチゴポッキーも、 まだ開けない。「田中さん」 静
-
 連続税務小説 ヤマゲン 第30話「税務調査が終わったあとに“必ずやるべきこと”」
税務調査が終わった翌日。 田中 恒一は、 何もない事務所で、 一人、机に向かっていた。 調査官はいない。 書類
連続税務小説 ヤマゲン 第30話「税務調査が終わったあとに“必ずやるべきこと”」
税務調査が終わった翌日。 田中 恒一は、 何もない事務所で、 一人、机に向かっていた。 調査官はいない。 書類
-
 連続税務小説 ヤマゲン 第31話 「青色申告を、甘く見た日」
月末の夕方。 田中 恒一は、工場の電気を一つずつ落としていた。 機械の音が止まり、 静けさが戻る。 その静け
連続税務小説 ヤマゲン 第31話 「青色申告を、甘く見た日」
月末の夕方。 田中 恒一は、工場の電気を一つずつ落としていた。 機械の音が止まり、 静けさが戻る。 その静け
-
 連続税務小説 ヤマゲン 第32話 「法人にした方がトクなんですか?」
昼過ぎ。 町工場に差し込む日差しが、 以前より少し強く感じられた。 機械の音は止まらない。 注文も、 問い合
連続税務小説 ヤマゲン 第32話 「法人にした方がトクなんですか?」
昼過ぎ。 町工場に差し込む日差しが、 以前より少し強く感じられた。 機械の音は止まらない。 注文も、 問い合
竹岡税務会計事務所
経営が見えない!を数字でクリアに。
まずは、お気軽に無料相談を。
電話番号:090-7499-8552
営業時間:10:00~19:00
定休日 : 土日祝
所在地 : 大阪府富田林市須賀1-19-17 事務所概要はこちら
